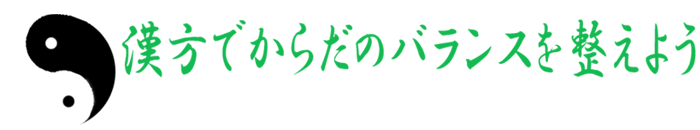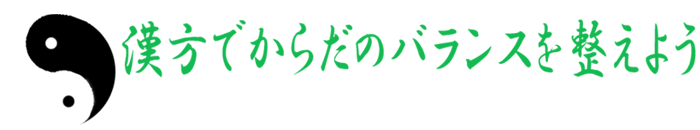|
|
 |
| こころの病気「不眠」 |
 |
不眠は、中医学や古典において「失眠」「不寐」「不得眠」などと表現されています。
中医学では一つの病証としてとして扱われる不眠ですが、それ自体は’標’(=結果として現れた病証・症状)であり、その原因としては、精神・神経的な過度の緊張や興奮などの心因的な要素に加え、胃腸症状や各種の痛み、月経などに随伴した二次的なものや、体質など’本’があり、それらが不眠症状に強く反映します。
その為、不眠の中医学的な治療に際しては、不眠に随伴する症状その他から背景となる病態、’本’を弁別して、その部分を改善することが需要です。
中医学において不眠は、「心神不安」(精神や神経が不安定な状態)として捉えられますが、臨床的には、虚では主に陰血不足が関係し、実では肝鬱、痰飲(食滞)、心火亢盛などが認められます。
また、臓腑としては、主に心脾肝胆腎が関係しています。
中医学による不眠の治療は、西洋医学で使われる睡眠や鎮痛薬のように睡眠を誘導する力では及びませんが、自然な眠りを妨げている病態に働きかけることにより不眠症状を改善します。
|
|
 |
不眠とは満足する睡眠がとれない事で、睡眠時間が短くても満足した状態であれば不眠ではなく、逆にはた目にはよく眠っているように見えても本人が不満であれば不眠です。
眠りの障害には、寝つきが悪くてなかなか眠れない、睡眠が浅くてすぐ目が覚めてしまう。睡眠時間が短くて朝早く目覚めてしまうなど様々な訴えが見られます。
五臓の一つである心が精神・意識・思惟・睡眠(心は神明を主る)などの活動を主っています。
陽気が盛んな日中は、心神が活発であり眠ることは少なく、陰気で盛んになる夜間には、心神が安静になって眠りに入ります。
安静になるべき夜間に何らかの原因により心神が乱されると、不眠が発生することになり、古人は「けだし寝は陰にもとづき、神はその主なり、神安んずれば則ち寝る、神安んぜざれば則ち寝ず。」といっております。
不眠に関係する像火はこころを中心にして肝・胆・脾・腎の機能が失調することによって生じます。
※上記表は、あくまで目安です。一人一人の証に合わせるには、お電話又はお問い合わせよりご相談下さい。 |
|
|
Copyright (c)2004 Yamoto-P Co. Ltd. All Rights Reserved.
|
|